地域創生の街を歩く
醸造の町 長岡市 摂田屋
12月に入る頃から雪国新潟は、天候が一変する。
西高東低の気圧配置となって、日本列島に等圧線(黒い線)が縦縞模様に走る。
太平洋側は、乾燥した好天が続く一方、日本海側は一転して寒くなり降雪が続く。
既に11月も下旬に入ると冬支度が始まる。車は冬タイヤ(スタッドレス仕様)に交換し、
車の雪を落すためのスノーブラシ、雪かきのスノーダンプ、スコップ等を積んでおく。
雪による庭木の保護をするための竹囲い(竹の枝を使い寒さや雪などから樹木を守る方法)
も行わなければならない。また今年も冬将軍が遠征してくる。
さて、12月の上旬天候の安定した日を選んで、電車で30分ほどにある
長岡市の宮内駅から直ぐの摂田屋地区を散策することが出来た。
全国有数の米どころとして知られる新潟県長岡市は、日本酒はもちろん古くから
醤油や味噌づくりも盛んな処である。特に摂田屋地区では、歴史ある酒造りの
蔵元や味噌、醤油等発酵等、麹の香り漂う“醸造の街”として近年脚光を浴びている。
その街並みは関東へ向かう旧街道としての「旧三国街道」と呼ばれ親しまれてきた。
古くは、北越戊辰戦争の際、長岡藩の本陣跡「光福寺」や鏝絵の蔵
「旧機那サフラン酒本舗」等、登録有形文化財や歴史的な建造物が遺る歴史の街でもある。
更にこの地区は、昭和20年8月1日の「長岡大空襲」を奇跡的に免れたエリアでもある。
さて、私の歩いたコースを簡単に紹介してみたい。
JR宮内駅を下車。10分ほどで江戸期からの醬油屋「越のむらさき」へ。
130年以上経過の趣きある外観を見て、むらさき醬油を購入。そこから徒歩5分の
鏝絵の蔵「旧機那サフラン酒本舗」を見学。産業王“吉澤仁太郎”はサフラン酒の製造販売で
稼いだ金を惜しげもなく注ぎ込み「鏝絵の蔵」に代表される仁太郎ワールドを作り上げた。
サフラン酒は、サフランの草を漬け込んだ薬酒で明治の2大ヒット商品と言われた。
徒歩6分で越後雪紅梅の長谷川酒造へ、重厚な赤レンガに囲まれた「麹室」がある。
越後雪紅梅を購入。更に徒歩5分ほどで北越戊辰戦争での長岡藩本陣跡「光福寺」で当時を偲ぶ。
長岡藩総督 河井継之助は、ここで「長岡藩は、義によって戦う」と宣言した。
徒歩10分で「吉乃川 酒ミュージアム『醸蔵(じょうぐら)』」へ。今や清酒「吉乃川」は、
新潟を代表する知名度を誇っている。ここでは吉乃川醸蔵でしか買えない
酒醸蔵限定生原酒を購入。最後は、老舗の新潟笹団子の「江口だんご」で抹茶を飲みながら
焼きたてのお団子を食した。麹の香りのする街並みを散策しながら
移動もすぐにできた丁度良いプチ観光となった。
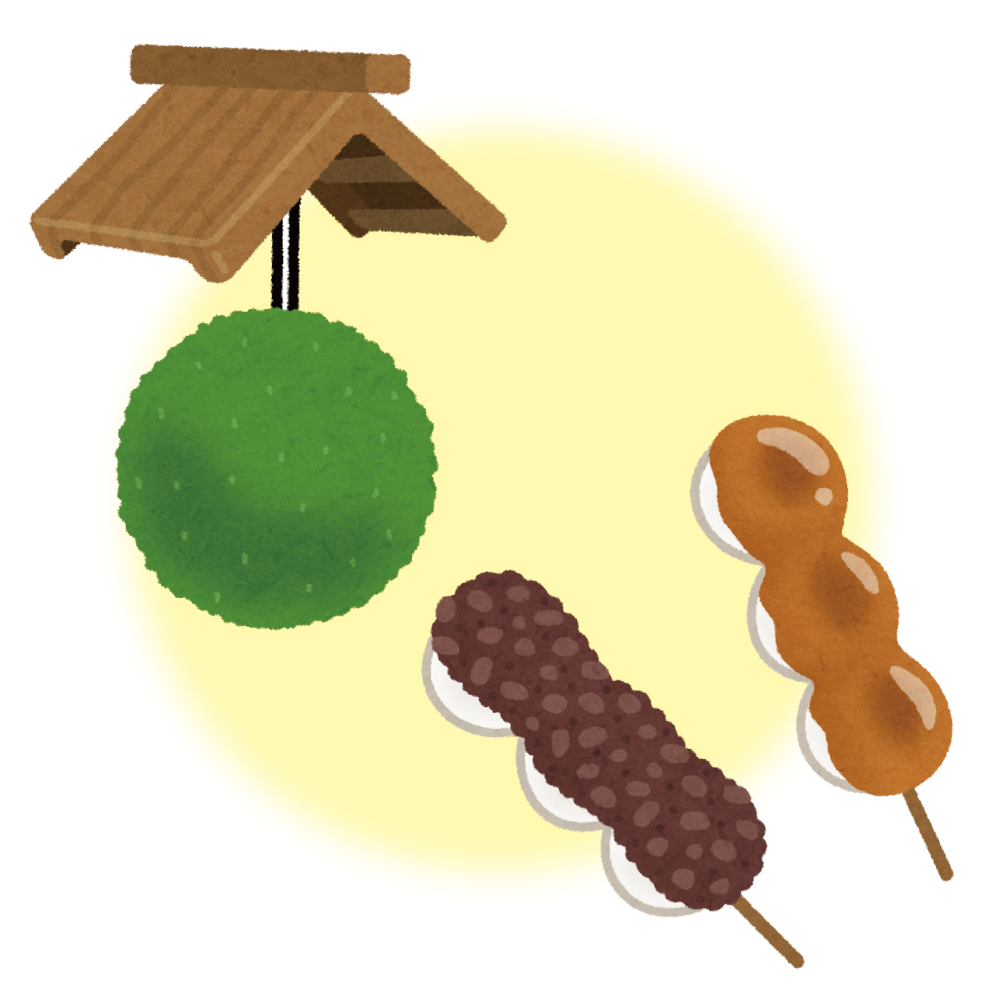
散策しながらつくづく石破首相が柱として掲げる地方創生は必須課題と感じた。
雪解けの終わる来年の春には、改めてここで「雪国の春」を満喫してみよう。
尚、散策コースでは、ボランティアガイドも整っている。SNS等で検索してみて欲しい。

 読み物
読み物 探す
探す